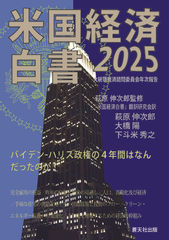4月の新刊
4月の新刊
4月の新刊


101-0051 千代田区神田神保町3丁目25-11
蒼天社出版
TEL 03-6272-5911 FAX 03-6272-5912
喜助九段ビル
更新日:2023年11月20日





アメリカ国際資金フローの新潮流
前田 淳(北九州市立大学経済学部教授)著
出版年月2016年
ISBNコード978-4-901916-47-9
本体価格 3,800円
A5判
頁数・縦256
著者紹介
前田 淳(まえだ じゅん)
北九州市立大学経済学部教授、博士(経済学)
1961年生まれ。九州大学経済学部卒
主な著書に、「現代の国際金融・資本市場と金融機関」(奥田宏司・神澤正典編『現代国際金融――構図と解明』第7章、法律文化社、2010年)、「変動相場制と国際金融構造」(信用理論研究学会編『金融グローバリゼーションの理論』大月書店、2006年)など。
内容
金融のグローバル化・規制緩和とIT化の潮流は、数十年の歳月を経てさらに続いている。日々、巨額の資金が、世界中を動き回っている。その結果、国際的な資金の流れは、各国の経済発展や為替レートに大きな影響を及ぼすものとなっている。このような国際資金フローの中でアメリカ経済とドルの果たしてきた役割は、極めて大きい。本書の課題は、このように重要な影響力を持つアメリカの国際資金フローの構造と変化を明らかにすることである。すなわち、どのような経緯と装置によってその構造が形成・維持されてきたのか、そして、2000年代末の世界金融危機の展開によって、その構造は変化しつつあるのかを分析する。
とりわけ注目したのは、アメリカが国際資金フローの中に、深くビルトインされていたということである。アメリカへの資本流入によって、アメリカ経済の成長や企業の資金調達は、加速されてきた。そのことは、対米輸出などを梃子に、多くの国の経済発展を促し、各国のドル準備の増加にもつながった。同時に、アメリカからの世界各国への対外投資によって、投資先の国と企業は成長・発展し、アメリカの所得収支において巨額の黒字をもたらしてきた。こうした相互促進的とも見てとれる構造が、今後も継続するのかどうかは、アメリカ経済のみならずドルの基軸通貨としての先行きや国際金融システムにも大きな影響をもたらす可能性がある。こうした理解と問題意識を踏まえて、本書は展開されている。
目次
序 章 課題と構成
第1節 課題と視角
第2節 先行研究
第3節 本書の構成
第1章 アメリカを中心とした国際資金フローの形成
第1節 問題の設定――アメリカの国際資金フローの構造はどのように形成されたのか
第2節 レーガノミックスと金融引締めによるアメリカへの資本流入の大規模化
第3節 アメリカへの資本流入がもたらした国際資金フローの構造変化
第4節 結 論
第2章 アメリカへの資本流入の諸要因
第1節 問題の設定――アメリカへの資本流入はなぜ続いたのか
第2節 民間レベルの資本流入――諸外国との金利差と為替レート予想変化率
第3節 公的レベルの資本流入――公的国際通貨としてのドルの機能
第4節 結 論
第3章 アメリカの対外証券投資の始動と展開
第1節 問題の設定――アメリカの対外証券投資の構造と要因
第2節 アメリカの国際資金フローの構造を規定した直接投資の展開
第3節 アメリカの対外証券投資はなぜ安定的なのか
第4節 結 論
第4章 アメリカの対外負債の持続可能性と国際資金フロー
第1節 問題の設定――経常収支赤字と対外負債残高の何が問題なのか
第2節 アメリカの対外負債の発散と収束
第3節 アメリカへの資本流入と経常収支赤字および対外負債のバランス
第4節 結 論
第5章 アメリカの国際資金フローの新局面――2007年以降の展開
第1節 問題の設定――アメリカの国際資金フローは構造を変えたのか
第2節 国際資金フローの変化を測る諸視角
第3節 アメリカへの資本流入の地域別・形態別変遷
第4節 結 論
理論』大月書店、2006年)など。
『日本占領期性売買 GHQ関係資料』
16社協賛
出会った本はみな新刊だ!
専門書販売研究会は、2000年に人文・社会科学の専門書を発行している版元の4人の発起人によって「4社の会」として発足しました。小社の代表取締役である上野もその一人です。近年の、市場環境の変化は、専門書販売にとって厳しいものになりました。しかし長年研究を重ね出版された研究書・著作をうずもれさせてしまっては社会的損失と思い、「はじめてあった本は、いつも新刊」として読者へ・研究者へ・図書館へ書籍情報を発信することにしました。会員も増え「専門書販売研究会」と名称を変え、分野も多彩になり哲学・歴史・経済・農業・芸術まで網羅した会となりました。現在は16社で専門書の販売のための研究・情報を共有する活動をしております。
これからも、コンセプト「はじめてあった本は、みな新刊」のもとに、日ごろ目にすることのない既刊書の再チャレンジを目指し、「こんな本もあったんだ」と言っていただけるように読者との出会いを目指します。